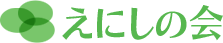会員様のご家族様からメールを頂きました。
最近はお子様がいらっしゃっても様々な事情でお父様やお母様、ご兄弟の支援をさせて頂くことが増えております。
このようなメールを頂き職員の励みになります。
こちらこそありがとうございます<m(__)m>
↓
狭心症を患っておられるH様。
日々の生活にとても気を配られ生活されています。毎日お野菜中心のお食事を摂り入れた自炊をされ、
愛犬と一緒のお散歩が毎日の日課にされているパワフルなH様です。
先日、初めて外出同行支援をさせていただきました。
お迎えの際、「娘も一緒に連れて行くよ!」と言われ戸惑っていると、H様の愛犬の事でした。
H様の声掛けにとても尻尾をフリフリ大喜びの愛犬。長年一緒に暮らし、娘みたいな存在なんだよねと
H様は嬉しそうにおっしゃいます。
私から拝見してもH様と愛犬とのコミュニケーションは正真正銘の家族そのものでした。
四六時中一緒にいるお互いのプラス効果は日々充実されていることでしょう。
「信頼がおける人とのコミュニケーションがあることで、安心感が保て年齢を重ねても孤独を感じることなく、老いることが楽しみになるよ」と笑顔でおっしゃっているH様に心打たれました。
私は自分の大切な人が理想とする老い方をどのようにお手伝いできるでしょうか。考えさせられました…
今も会員様とはコロナ禍での様々な制限の中、なかなかお会いすることができません。
限られた支援の中でこそ、改めて家族代わりとして支え、より安心していただけるよう努めて
いかなければと思いました。
何気ない日常の中で様々なことを共有しながら会員様の思いや考えに寄り添いながら
これからも感謝の心を持ちサポートさせていただきたいと思います。
お元気でしょうか? 今まで大変お世話になりました。 私が海外赴任となり、妹も当時は障害を持った子供を抱えており、父のケアをどうするかが1番の気がかりでしたが、 〇〇さんをはじめ〇〇さんにも本当に良くして頂き、父のみならず我々も大変心強かったです。 えにしの会に出会えたことに心から感謝してます、どうもありがとうございました。 これから暑い夏となっていきますが、くれぐれもお体をご自愛ください。 〇〇〇〇A様のご相談を頂いたのは、病院の相談員様からでした。 入院中にADLが下がり、施設への入所が決まった男性がいるが保証人がいない。 奥様は特養にご入所されており、息子様はおられるが疎遠で保証人をされない。 えにしの会の事をお伝えした所、入所希望の男性、息子様、共に契約を了承して下さった との事でした。 病院でA様とお話し。えにしの会と契約を行い、施設入所のお手伝いをさせて頂きました。 その後、A様とは通院のご支援や色々な外出支援などを行いました。 中でも特養にご入所中の奥様の面会に行かれる外出支援を楽しみにされていました。 程なくして、A様は体調を崩されご逝去される事になります。 息子様とのお話の中で、お葬儀は息子様が、それ以外の役所関係含め各種手続きなどは えにしの会がお手伝いさせて頂くこととなりました。 お葬儀後に息子様にお話した内容がとても印象深く、今でも覚えています。 「以前は父と色々な過去があり、とても自分一人で父の面倒を見るという気になれなかった。 しかし、えにしの会に入って貰って自分一人で父の面倒を見なくていいと思えたら とても気が楽になった。最後の最後になったが父と向き合えたのはえにしの会のお陰です」 ご家族には色々な形があります。 これからも、2つとして同じ形のないご家族に対する支援を続けていきたいと思います。
K 様は高齢者向けシェアハウスに入居されています。 月 に 一 度 外 出 し 、生 活 必 需 品 な ど の 購 入 や 散 髪 、何 よ り 昼 食 時 に 飲 む ノ ン ア ル コールビールが楽しみだと仰います。 外 出 日 に 施 設 へ お 迎 え に 行 く と 、い つ も 玄 関 前 の ベ ン チ に お 掛 け に な っ て お り 、 満面の笑みで「楽しみに待っていたよ」と声をかけてくださいます。 あ る 日 、い つ も と 同 じ よ う に 買 い 物 を 終 え 、昼 食 を と る 際 に 「 今 日 は ノ ン ア ル コ ー ル ビ ー ル は 飲 ま な い 」 と 仰 い ま し た 。 気 分 を 害 さ れ た の か と 心 配 し ま し た が 、 「 早 め に 店 を 出 て 、 近 く に あ る 公 園 の 大 き な 桜 を 見 て 帰 り た い 。」 「年 に 一 度 し か 見 る こ と が で き な い 。」 「毎 回 見 れ る の が 当 た り 前 と 思 わ ず 、日 々 を 大 切 に し な く ち ゃ ね 。」 私 は そ の 言 葉 を 聞 い て 、当 た り 前 に な っ て い る こ と 大 切 に し て い こ う と 思 い ま し た 。 支 援 の 時 間 が よ り 良 い 時 間 に な る よ う に 考 え る こ と の 大 切 さ を 再 認 識 し た支援でした。
男性会員様のA様が難病を抱えて、施設入居されました。 施設に入居すると、おのずと行動範囲が狭まりますし、体のきつさもあって 自分がしたいことを伝えることができなくなってきていました。 面会に伺っても言葉が少なくなり、お声も小さくなってました。 毎日ベッドの上でじっとしている日々を過ごされていました。 ご両親、ご兄弟を亡くされてますのでご家族の縁が薄く寂しさを感じているようでしたので、 Aさんになんとか笑顔になって貰えることはないかと考えていました。 ある時、Aさんとの会話の中で「誰か会いたい人いますか?」と聞いたところ。 「姪に会いたい」と答えられました。 姪御さんの電話番号は知らないようでしたが、ご実家の電話番号は知っている とのことでしたので、私が連絡させていただくと伝えましたが、 Aさんは、「いいよ。連絡しなくて」とおっしゃいました。 実は、えにしの会への入会は施設入居の際に、手紙で姪御さんに身元保証人を頼んだが断られ、 それでえにしの会が身元保証人となり施設に入居された経緯がありました。 結局、連絡だけしてみますねと伝え、Aさんも小さく頷いてくれました。 後日、姪御さんと連絡がとれ姪御さんから聞いた話しをAさんに伝えに伺いました。 電話でお聞きした話をそのまま伝えましたが、 その話しを聞いて、いつもは無表情のAさんが突然こらえきれなってむせび泣きされ、 大粒の涙を流されました。 Aさんは、ずっと施設入会の身元保証人を断られたことで、姪は自分のことを良く思ってない。 嫌っていると思われていたみたいです。 姪御さんの話では、身元保証人を断ったのは、その時にご自身も親の介護やお子さんの 受験などがあり、そんな中ではちゃんと面倒をみてあげることができないし、中途半端に 関わることはAさんの為にはならないという想いから身元保証人を断られたようです。 実際にすごくAさんのことは気に掛けていらっしゃいました。 自分のことを良く思っていないということではなく、やむをえないことがあったとのことを知れて、 今までのわだかまりが消えたようでした。 その後、施設に姪御さんがご家族と面会にきてくれて数年ぶりの対面を果たされました。 姪御さんやご家族と話をされる時には、いつもは体のきつさから小さい声しか出せなかった Aさんでしたが、再会ができて本当に嬉しかったようで、声をはりにこやかに楽しそうに 話されていました。 私もそんな素敵な場面に立ち会わせていただき、Aさんの心からの笑顔が見れて、 とても嬉しく思いました。
A様とB様は、高齢者施設に入居されているご夫婦です。
娘様がお一人いらっしゃるも、外国で生活をされているため日常的な支援や緊急時の駆けつけが難しい状態。
そのため、今後はえにしの会が娘様に代わりサポートしていくことになりました。
普段は面会や病院受診の付き添い、役所関係の手続きなど、日常的な支援を娘様に代わってサポートしています。
ある時、施設から「A様の体調がよくないため緊急搬送します」との連絡が入りました。
私は、外国にいる娘様に連絡を取りながら病院へ駆けつけましたが、残念なことにA様はお亡くなりに。
コロナの影響もあり、娘様の来日は最短でも1ヶ月ほどかかるとのこと。
そのため娘様と相談し、葬儀はB様とえにしの会で執り行い、娘様が来日してからご希望の納骨先へ納骨する流れとなりました。
娘様が来日するまでに、えにしの会でA様の死後事務手続きを行いましたが、相続については娘様が来日しなければできないという問題がありました。
そのため、各関係先と調整をして娘様の来日までに必要書類を用意し、娘様の限られた滞在期間中に無事に終えることが出来ました。
娘様には「書類を準備してもらったおかげでスムーズに手続きできた。お世話になりました」と声をかけていただき、
B様からも「娘が外国にいるので一人では不安だった。ありがとう」と感謝のお言葉をいただきました。
今後もB様の気持ちに寄り添いながらサポートさせていただきます。
えにしの会では会員様のご逝去後に、ご希望のお葬式を行うためのお手伝いもさせていただいております。 最近ではとある会員様が、以前に通われていた教会でのお葬式をしたいとのご希望があり、 そのお手伝いをさせていただきました。 体調が芳しくなく時間もあまり無い中でしたが、教会の牧師さんと連絡をとり、費用面の確認や、 ご親族、葬儀会社との連携等のサポートをさせていただきました。 今となってはご本人様に直接聞くことは叶いませんが、葬儀に参列されたご親族やご友人の皆様の表情やお話の内容から、 少しでもご希望に寄り添ったご葬儀ができたのではないかと感じております。 今後とも会員様のご希望に寄り添っていけるよう、日々のコミュニケーションを 大事にしていきたいと感じたご支援でした。
12月中旬の、とある日の夕方。
事業所にI様がご入居中の施設からお電話が入りました。
「今から緊急搬送になります、救急車を呼びましたので対応をお願いします」
連絡を受けてから約1時間後、施設に着くとそこにはまだ救急車の姿が!
中には、担架に乗せられ呼吸器を付けて苦しそうなI様の姿がありました。
コロナ禍の影響で、中々病院が決まりません。
それから病院が決まるまで約30分、搬送に更に30分。呼吸が辛そうなI様と一緒に、
病院へ向かいました。
I様は言葉は上手く発せられないながらも、こちらの呼びかけに時折頷く様子もありました。
病院での対応が終わり、帰り際にI様のご様子をお伺いできました。
「頑張りましょうね」
I様は小さく頷いたように見えました。
それから1週間後、病院で懸命の治療を続けましたが、I様はご逝去されました。
コロナ禍で面会もできず、あれ以来お会いすることはできませんでしたが、
あの日救急車で搬送される最中の不安を、少しでも取り除けたのだろうかと考えます。
会員様の生活に寄り添う支援を、これからも心がけていきたいと思います。I様と初めてお会いしたのは半年ほど前です。
奥様の後押しもありご夫婦で契約していただきましたが、契約後もお電話すると、手伝ってもらうことはないから来なくて大丈夫との一点張りでした。
奥様にご協力いただき、ご自宅に顔を出し、コミュニケーションを取るうちに 今の生活のこと、不安なこと、できなくなったことお話してくださるように。
「書類の管理をしたいけどできなくなってきた」 本当はご自分で行いたいとのことでしたので、 今では私がお手伝いさせていただく形でI様に管理していただいています。
物忘れがありなかなか名前が覚えられないとのことでしたが、 今では笑顔で名前を呼んでくださります。
「あなたがきてくれると家がパッと明るくなるよ。いつもありがとう。」 そう言っていただいた時は、 少しでも支えになれているのかな、本当によかったと思いました。 これからもお二人とも笑顔で生活していただけるよう支えていきたいと思います。病院のソーシャルワーカーからえにしの会へ「入院中の患者様が、退院後の生活に不安があるのでサポートできるか聞きたい」とご相談がございました。
詳しい内容はご本人から話したいとの事で、後日病院で面談を行うことに。
面談日、不安気な表情を浮かべて面会室に来たS様は、日々の生活や終活へ向けての不安をたくさんお話くださいました。
退院後の一人での生活が不安。ご主人様とお子様方を先に亡くされ、施設に入る際の保証人も誰もいない。納骨先のお寺との手続き。ご主人様の相続手続き。など
私たちが終身に亘って保証人を法人でお引き受けできることや、お寺との話合いや相続に関してもサポートできることをお伝えし、ご入会いただきました。
まずは、退院後の生活について。
施設を検討されていましたが、S様は思い出が詰まった家で生活を続けることを理想とされていた為、ケアマネージャーと相談し、ヘルパーを利用することにより、家で生活できる環境を整えました。
次にお寺に関して。
ご主人様とお子様方の永代供養の手続きが済んでいなかった為、住職さんと直接お話の場を設けていただき、私たちが同席のもと、S様の望む形で手続きをすることができました。
相続に関しては、法定相続人20名以上に遺産分割がされる形で進んでおりましたが、S様がご主人様の作成した遺言公正証書を持っていた為、相続に関わっていた弁護士に相談し、遺言公正証書の内容の通り、S様お一人に相続されることになりました。
今は、お悩みも解決され、ご自宅で快適に生活をされております。
月に一度の病院受診同行の際は、とてもにこやかに普段の生活のお話をしてくださっております。
「安心した。あなた達に頼んでよかった。本当に助かった。ありがとう。」
お会いする度に、S様が私たちへかけてくださる言葉です。