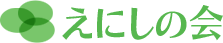ご自分の終末期はどうのように迎えるのか?というテーマについて、皆さん考えられたことはありますか? 自宅、病院、それとも老人ホーム?その時の環境で場所を選ぶというのはなかなか想像しにくいですよね? 横浜事業所の会員様で末期ガンの方がいらっしゃいました。 身寄りが遠方にお住まいの方で、どうしても最期を自宅で過ごしたいという強い意志のある会員様でした。 本来なら、ホスピスも選択肢にありましたが、その会員様の意志を尊重するために、その会員様を取り巻く あらゆるサービスを活用して協力し合いました。 24時間体制で自宅でヘルパーや訪問看護が最期まで支えていく体制づくりをしました。 自宅で最期を迎えることは、医療的にも万全なケアができる訳ではありませんが、会員様を最後まで支えて いくことが出来たことは、本当に良かったと感じています。 これからも、気持ちに寄り添う支援に取り組んでまいります。A様と最初にお目にかかったとき、A様はとても大きな、そして漠然とした不安を抱えられておられました。 A様はお一人暮らしで頼れる親族がおらず 「自分に万が一の時があった時にどうなるのか?」 それが気がかりでずっと不安を抱えておられたとの事でした。 「A様が一番不安に思われていることはなんですか?」 とお伺いした時のお答えが「葬儀をやってくれる人がいない」と言う事でした。 A様が望むお葬儀の形をお伺いし、それに必要な契約、手続きなどを説明。 そこからは「他にご不安な点はございませんか?」と、じっくりお話をお伺いし一つずつ ご不安に思われている項目に対する「えにしの会が出来ること」をご説明させて頂きました。 今まで漠然と感じていた不安に対して、一つ一つ具体的に解決する方法をご説明させて頂くうちに A様のご不安はいつの間にか無くなったご様子でした。 ご入会頂いた後、A様からは 「えにしの会へ入会して不安がなくなり安心した。本当に良かった。」 と仰って頂きました。 これからの生活においてA様が不安を覚えられることがあるかも知れません。 その際もA様に寄り添い、不安な気持ち安心に変えられる支援を提供して行きたいと思います。
他県にお住まいであったり、近くにお住まいであっても支援できないご事情のあるご親族様方に代わって、
病院受診やお買い物など支援させていただくことがあります。
昨今のコロナ禍で他県からのお見舞いが叶わず、病床の会員様を心配されていたり、
病状の変化に困惑されるご親族様…
そのような状況で、ご親族様への電話やメールでのご報告も大切な支援であると感じています。
病状の詳しい説明を求めていらっしゃる場合は、再度病院へお尋ねしてご報告したり、支援時に
お会いした会員様のご様子をお伝えすることで少し安心していただけることもありました。
また、会員様を会員様支えてくださっている医療関係・福祉関係の方々、民生委員やご近所の方々などとの
連携により、会員様を取り巻く環境の改善が見いだせるケースもあり、そういった関係者の皆様とご親族様とを
繋ぐ支援の重要性も感じています。
もし自分がご家族だったら…と思いを馳せながら、ご親族様方の”本当は近くで見守りたい”
お気持ちに少しでもお応えしたいと思っております。
去年の末頃、新しくとある方の支援をさせて頂く事になりました。 初めてお会いしたのは、施設へお引っ越しをされるとの事で、自宅の荷物の整理や 持ち出しの支援でした。 その後も病院受診の付き添い等で何度か支援をさせて頂いていました。 支援の回数が増える度に会話も増え、昔タクシーの運転手をしていた事を教えて頂きました。 買い物や病院までの付き添い中に、 「ここの道を通るのは懐かしい」「この道のこの時間は混むからあっちを通った方がいい。」 など長年タクシー運転手をしてきたからこそ分かる事等を教えて頂きました。 私達も多くの会員の方々の支援をさせて頂いており、毎日車を利用して移動しています。 その為、この方からのお話はとても貴重で学ばせて頂く事が出来ました。 今回支援させて頂いた方に限らず、普段から対応させて頂く会員様は目上の方ばかりなので、 自分が知らない様な事や貴重な話を聞かせて下さいます。 仕事をしながら多くの人と会話したり触れ合う中で、勉強させて頂く事が多く 日々感謝しなければと改めて思いました。 今後も感謝の気持ちを持ち、皆さんにしっかり寄り添って支援をさせて頂こうと改めて思います。
もともとはご夫婦での会員様で別々の施設に入居されていました。
ご夫婦より二人で一緒に生活できる施設を探してほしいとのご希望あり。
ケアマネ、施設相談員と協力しご希望の施設を探すこととなる。
候補の施設が見つかり施設見学の付き添い。
当日中に仮申し込みを行い、その施設へ入居することを決断される。
引越しのお手伝いを行い、無事に入居完了。
希望通りご夫婦での生活が再スタート。
入居後は病院受診の付き添いや定期的な面会でサポートを行う。
ある日、ご主人様が体調を崩し緊急入院。
M様と病院へ駆けつけるもそのままお亡くなりになられる。
葬儀を行いM様ご夫婦の納骨堂があるお寺へM様と一緒にご主人様を納骨。
定期的にM様とお寺へお参りに行き、そのたびに元気だったころのご主人様の話をしてくださいます。
M様にはご主人様の分も長生きしてほしいと思います。
私がM様(60歳・女性)とお会いするのは、いつも手術の立ち会いの時です。
M様は20代の頃に糖尿病と診断を受けていましたが、放置していたそうです。
気付いた時には手遅れで糖尿病の様々な合併症を発症していました。
ある日、いつものように透析へと、ご主人の送迎で向かわれたM様でしたが、定時が過ぎてもご主人のお迎えはなかったそうです。
すでにご主人は自宅で倒れて帰らぬ人となっていました。
M様は子供、頼る親戚が近県にいらっしゃらないことから弊会に入会されました。
M様は、お笑い好きでユーモアセンス抜群な、年下の私が言うのも変ですが、とても可愛らしい女性です。
お会いする時は必ず一言メッセージがプリントされたTシャツをお召しになっており、シュールな笑いを提供して下さいます。
正直なところ、お会いするまでは、病気に対するマイナスイメージが強く、勝手に物静かで暗い人をイメージしてしまっていました。
ご主人との突然の別れでの環境の変化、透析で疲れた日、幻肢痛・狭心症の発作で眠れない日も多いはずですが、お会いする際はいつも明るく、必ず労いの言葉を掛けて下さいます。手術の日は、不安と緊張でいっぱいのはずですが、私を気遣って下さいます。
先日立ち会った手術は、心臓のカテーテル治療でした。狭くなった血管をバルーンで拡張する手術でしたが、糖尿病のM様にとっては、命の危険もある大きな手術ということでした。
当日も私に、「忙しいところごめんね。お昼ごはん食べて来た?」と労いの言葉を掛けて下さるM様。 カテーテル検査は何度か受けているそうですが、今回の手術は事前にリスクが大きいことを主治医から説明を受けており、私も事前にM様、M様のお兄様から何度か相談を頂いており、とても不安が大きい様子でした。
手術は何とか無事に終えることができました。局所麻酔で行われたそうですが、「手術中に主人の呼ぶ声が聞こえてね、もう頑張らなくてもいいんだよと言われている気がしたの」 と話してくれました。
その言葉に私はどう声を掛けて良いか正解が分からず、ただ傾聴していました。
退院日もご支援させていただきましたが、後ろ向きになったのはその日だけで、M様は前を向いていました。
「私、愚痴とか聞いてくれる話し相手が欲しいの。」
「話し相手なら私がいくらでもなりますよ」と返事をすると
新しい出逢いが欲しいなぁと冗談交じりでおっしゃっていました。
ご縁でM様と出会いましたが、M様の支援では、いつも自分自身の在り方を見つめ返す機会を頂いているようです。
M様に「ありがとうございました」とおっしゃって頂きますが、こちらがいつもありがとうございますという気持ちでいっぱいです。
コロナ渦ということもあり、簡単にはお会いできませんが、これからもM様にとって少しでも心の拠り所となれるような支援を志したいと思いました。
白内障の手術後の様子と視力低下の状態を診てもらうために定期的な病院への通院支援をさせていただいているS様は有料老人ホームにご入居されています。
S様はなかなか外出の機会が少なく、外出の際はいつも楽しそうにお話をされています。
病院受診の後に売店などで購入した物を食べたり、買い物に行くのが楽しみだと仰られていました。
しかし昨今の世間の情勢や、施設の方からのお願いもあり病院受診の後そのまま帰ることに。
S様も最初はご納得されていましたが、帰る途中で衣服を買いに行きたいとのお話が。
衣服は試着が必要になるので代わりに購入することは難しいです。
どうしたらよいかと考えた末、施設の方に電話してあることをご相談しました。
そして電話を済ませて、近くの衣料品店に向かうことに。
S様には車の中でお待ちいただいてお店の方に事情をお話しし、「車の中で試着をさせてもらえないか」というお願いをしました。
結果、お店の方同伴の条件つきでOKがいただけました。
そしてS様にご満足いただける室内用の上着を購入することが出来ました。
その時のS様の表情と「いろいろやってくれてありがとうね」というお言葉は今でも時々思い出しては励みとなっています。
弊会の支援が会員様にとって普段と異なる「非日常」であることもあります。
支援の時間がより良い時間になるように考えることの大切さを再認識した出来事でした。
えにしの会では、24時間365日に連絡緊急時の対応ができるように体制を整えております。
今回は、緊急搬送時の駆け付け対応について、ご紹介させて頂きます。
とある土曜日の夕方に横浜会員:Eさまが入居している施設の職員より、連絡が入る。
Eさまが、息苦しさを訴えていて、事前に主治医から指示を受けていたので、指示通りに酸素を吸入するも、からだの血中酸素濃度が上がらないため、救急車を呼んで、これからかかりつけ病院に搬送するとのこと。
付き添っている施設職員に連絡し、搬送先の病院にて合流することになる。
無事を祈りつつ足早に搬送先に向かい、搬送先の病院に到着。付き添いの施設職員と合流する。
Eさまのご様子としては、救急車にて搬送している間に、状態は少し改善され、病院に到着し検査など行ない、現在は処置室にて処置中とのこと。施設職員から、入院になった時に備えて用意したご本人さまの荷物をお預かりして、施設職員とはここで別れる。
当直の医師から、あらためて病状の説明を受け、誤嚥性肺炎のため、入院加療が必要とのこと。元々、手術のための入院が数日後に予定されていたが、病状の悪化によって、それが今回、早まった形となった。
肺炎の治療を優先しつつ、病状が改善したら、そのまま予定していた手術に向けていく方針とのことで、
医師からの説明は終わった。
処置室にて、ようやくEさまご本人と対面。
ベッドに横たわり、酸素のマスクをされ、やや息苦しそうだったが、意識はハッキリされ、お話しできる状態であった。病状と入院の説明を行ない、これから入院の手続きを行う旨を伝え、本人の荷物や必要なもの・貴重品の管理についてなど、打ち合わせをする。
コロナ禍で、入院する病棟には一緒に上がれないため、入院の準備を整え、そのまま処置室で戻る旨を伝えると、「来てくれて、ありがとう」とEさまから感謝を述べられて、退室する。
今回は、かかりつけの病院や施設の方のご協力も得られたこともあり、互いに役割を果たすことで、迅速に対応することができ、大事に至ることがありませんでした。
今後も関係各所と良好な関係をもちつつ、ともにEさまの生活を支える一員として、支援に取り組むようにと強く心に感じました。元々、他の身元保証会社との契約をされていたA様。
関東エリアでの支援継続ができなくなったことをきっかけにご入会いただきました。
新しい身元保証会社に切り替えることは、とても不安で心細かったと思います。
当初不安を常に口にされていましたが、受診の付き添いや買い物をご一緒することで、少しずつ心を開いてくださいました。
お住いの施設から車で外にお連れすると、道に詳しく地名や施設もよくご存じでいらっしゃるのでお聞きすると、5年前にご逝去されたご主人様がよくドライブに連れて行ってくださったとの事。
「いつも主人に頼ってばっかりで・・・」とおっしゃるA様のさみしげな横顔。
ご主人様を亡くされ尚のこと不安を感じていらしたのでしょう。
最近はオミクロン株の急拡大で面会も難しいのですが、お住いの施設事務所への訪問予定を伝えると、「私も玄関まで行くわ、会えるでしょう?」と私が行くことを歓迎してくださるご様子。
しかし、玄関には面会禁止の大きな張り紙。今はお会いすることもままなりませんが、早くマスクを外してお互い笑顔で話せる日が来ることを願うばかりです。
こうして頼りにしてくださる会員様に、心から信頼される支援員でありたいと強く感じました。Y様は、ご夫婦で入会していただいている会員様です。
お二人とも90歳を超えていますが、ご自宅で二人暮らし。
訪問介護、訪問看護などを利用しながら、病院受診や外出など介護保険外の部分はえにしの会で行うなど、連携をとりながらサポートをしていました。
あるとき、ご主人はご自宅で倒れ、そのまま息を引き取りました。
持病の心臓発作でした。
訪問看護にすぐに電話をくださり、駆けつけた看護師やわたしたちにもてきぱきと対応し、気丈にふるまっていた奥様。
お葬式が終わりしばらくしたとき、
「役所からの書類の書き方がわからないから教えてほしい」
と依頼があり、ご自宅に伺いました。
そのとき、奥様がぽつりぽつりとお話してくださいました。
得意だった料理は、ご主人のためだからリウマチで手が痛くても頑張れていたこと。
耳が悪く、ご主人がいないとチャイムの音も聞こえないこと。
実は手先が器用なのはご主人で、裁縫や細かい作業はぜんぶご主人がやっていたこと。
ご主人がいなくなってから、とても寂しく、何に対してもやる気が出ないこと。
私たちが見えていた部分以上に、心身ともに支えあって暮らしていたお二人でした。
「わたし、施設に入ろうと思うの。どうしたらいい?」
そうY様は続けました。
施設に入居されたことがなく、何から手を付けていいのか分からないとのこと。
ご希望を伺い、今後施設に入居するときの流れなどをご説明すると
「ありがとう。一人で心細かったの。けど、あなたたちがいてくれたら安心ね」
そういっていつもの元気な笑顔をみせてくれました。
これからも安心、信頼を感じていただける存在でありたいと強く思いました。